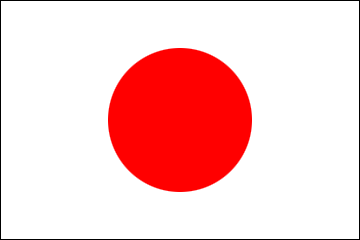主な証明
令和7年11月3日
当館にて扱っている証明書の主なものは以下の通りですが、その他の証明書につきましては、直接当館領事班へご照会下さい。
1.在留証明 (和文)
インドにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続、免税手続き※等の際に使用されます。
(1) 発給条件:申請者が当館管轄内(カルナータカ州)に既に3ヶ月以上滞在している、または、今後3ヶ月以上の滞在が見込まれていること(該当する方は、在留届の提出対象者ですので、事前に在留届の提出をお願いいたします)。原則、本人が出頭すること(来館が困難なやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください)。
(2) 必要書類:
・在留証明申請書(窓口に用紙があります)
・日本国旅券(原本)
・現住所を立証できる書類(FRRO発行のResistration Certificate / Residential Permit、氏名、現住所、発行日を確認できる電気、電話、ガス、水道などの公共料金領収書など、すべて原本)。なお、現住所の居住開始日も証明する必要がある場合は、居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書等)の原本が必要となります。
・証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本(原本)
(3) 所要日数:申請日当日
(4) 手数料:こちらをご覧ください(現金でお願いします)。
〈免税手続きにおける在留証明の利用〉
※日本国内における免税手続きは、2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類で確認できる方が対象となっており、「在留証明」または「戸籍の附票の写し」(いずれも原本)を提示する必要があります。国税庁は在留証明に「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載を求めていますので、免税手続きで在留証明を申請する際は、旅券、現住所を立証できる書類の他、必ず戸籍謄(抄)本をご用意いただくようお願いいたします。
詳細は観光庁HPをご確認ください。
-消費税免税制度についてのよくある質問(観光庁HP)
2.署名(及び拇印)証明 (原則、和文)
署名及び拇印が本人のものであることを証明するもので、日本の印鑑証明に相当します。本邦における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更手続等に使用されます。
形式1(貼付型。ご持参いただいた署名が必要な書類に、当館証明書を貼り付けるもの)、形式2(単独型。当館で用意した書式に直接署名等していただくもの)の2種類がありますので、どちらの形式が必要か、あらかじめ日本の提出先に確認して下さい。
(1) 発給条件:本人が必ず出頭する必要があります。(代理申請は不可。引取りは,代理人でも可。)
(2) 必要書類:
・本人を確認出来る公文書(旅券等原本)
・署名が必要な書類があれば当該書類(形式1の場合、署名欄空欄のもの)
(3) 所要日数:申請日当日
(4) 手数料:こちらをご覧ください(現金でお願いします)。
3.出生・婚姻・婚姻要件具備・死亡等の身分上の事項に関する証明 (英文)
身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもので、すべて外国関係機関あてで、外国文で発給されます。以下の種類があります。
・出生証明・・・いつ、どこで出生したかを証明するもの
・婚姻要件具備証明書・・・独身であって、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
・婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
・離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
・死亡証明・・・いつ、どこで死亡したかを証明するもの
・戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの
(1)発給条件:原則本人出頭、来館が困難な場合は代理人でも可
(2)必要書類:
・旅券等の身分証明書(原本。婚姻用件具備の場合は、加え婚約者の旅券写し)
・身分事項が確認できる3ヶ月以内に発行された戸籍謄本原本または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
(注)「符号」は総領事館窓口で提示します(オンライン申請の場合は、申請画面上で入力しオンライン提出します。符号を提出した場合、戸籍謄本原本は不要です。)。
(注)「符号」は行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。詳細はこちら別ウィンドウで開くから確認できます。
(注)「符号」はマイナポータル上(無料)別ウィンドウで開く又は市町村窓口(有料)で取得できます。詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。
(3)所要日数:申請日の翌開館日(※当日)
(4) 手数料:こちらをご覧ください(現金でお願いします)。
※受取り希望日の前開館日以前に当館領事メール(cgjblr@ig.mofa.go.jp)宛てに戸籍謄本(写)等必要書類を送付して頂く場合に限り、申請日当日に交付することが可能です。(併せて戸籍に記載されている方々の氏名のローマ字表記(パスポートをお持ちの場合は、パスポート上の表記)をお知らせください。また、外国籍の方が含まれる場合には、氏名の綴りが確認できる公文書(パスポート、在留カード等)の写しも添付してください。)
1.在留証明 (和文)
| ※令和7年5月27日以降に在留証明をオンラインで申請する場合は、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、電子化した証明書(e-証明書)をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になりました。 これにより、e-証明書を選択した場合は、申請者は在外公館の窓口に一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となりますので、ご利用ください。詳細はこちらから。 |
(1) 発給条件:申請者が当館管轄内(カルナータカ州)に既に3ヶ月以上滞在している、または、今後3ヶ月以上の滞在が見込まれていること(該当する方は、在留届の提出対象者ですので、事前に在留届の提出をお願いいたします)。原則、本人が出頭すること(来館が困難なやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください)。
(2) 必要書類:
・在留証明申請書(窓口に用紙があります)
・日本国旅券(原本)
・現住所を立証できる書類(FRRO発行のResistration Certificate / Residential Permit、氏名、現住所、発行日を確認できる電気、電話、ガス、水道などの公共料金領収書など、すべて原本)。なお、現住所の居住開始日も証明する必要がある場合は、居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書等)の原本が必要となります。
・証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本(原本)
(3) 所要日数:申請日当日
(4) 手数料:こちらをご覧ください(現金でお願いします)。
〈免税手続きにおける在留証明の利用〉
※日本国内における免税手続きは、2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類で確認できる方が対象となっており、「在留証明」または「戸籍の附票の写し」(いずれも原本)を提示する必要があります。国税庁は在留証明に「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載を求めていますので、免税手続きで在留証明を申請する際は、旅券、現住所を立証できる書類の他、必ず戸籍謄(抄)本をご用意いただくようお願いいたします。
詳細は観光庁HPをご確認ください。
-消費税免税制度についてのよくある質問(観光庁HP)
2.署名(及び拇印)証明 (原則、和文)
署名及び拇印が本人のものであることを証明するもので、日本の印鑑証明に相当します。本邦における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更手続等に使用されます。
形式1(貼付型。ご持参いただいた署名が必要な書類に、当館証明書を貼り付けるもの)、形式2(単独型。当館で用意した書式に直接署名等していただくもの)の2種類がありますので、どちらの形式が必要か、あらかじめ日本の提出先に確認して下さい。
(1) 発給条件:本人が必ず出頭する必要があります。(代理申請は不可。引取りは,代理人でも可。)
(2) 必要書類:
・本人を確認出来る公文書(旅券等原本)
・署名が必要な書類があれば当該書類(形式1の場合、署名欄空欄のもの)
(3) 所要日数:申請日当日
(4) 手数料:こちらをご覧ください(現金でお願いします)。
3.出生・婚姻・婚姻要件具備・死亡等の身分上の事項に関する証明 (英文)
| ※令和7年10月28日以降に出生証明、婚姻要件具備証明書、婚姻証明、戸籍記載事項証明をオンラインで申請する場合は、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、電子化した証明書(e-証明書)をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になりました。※「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力する必要がございます。。 これにより、e-証明書を選択した場合は、申請者は在外公館の窓口に一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となりますので、ご利用ください。詳細はこちらから。 |
・出生証明・・・いつ、どこで出生したかを証明するもの
・婚姻要件具備証明書・・・独身であって、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
・婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
・離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
・死亡証明・・・いつ、どこで死亡したかを証明するもの
・戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの
(1)発給条件:原則本人出頭、来館が困難な場合は代理人でも可
(2)必要書類:
・旅券等の身分証明書(原本。婚姻用件具備の場合は、加え婚約者の旅券写し)
・身分事項が確認できる3ヶ月以内に発行された戸籍謄本原本または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
(注)「符号」は総領事館窓口で提示します(オンライン申請の場合は、申請画面上で入力しオンライン提出します。符号を提出した場合、戸籍謄本原本は不要です。)。
(注)「符号」は行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。詳細はこちら別ウィンドウで開くから確認できます。
(注)「符号」はマイナポータル上(無料)別ウィンドウで開く又は市町村窓口(有料)で取得できます。詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。
(3)所要日数:申請日の翌開館日(※当日)
(4) 手数料:こちらをご覧ください(現金でお願いします)。
※受取り希望日の前開館日以前に当館領事メール(cgjblr@ig.mofa.go.jp)宛てに戸籍謄本(写)等必要書類を送付して頂く場合に限り、申請日当日に交付することが可能です。(併せて戸籍に記載されている方々の氏名のローマ字表記(パスポートをお持ちの場合は、パスポート上の表記)をお知らせください。また、外国籍の方が含まれる場合には、氏名の綴りが確認できる公文書(パスポート、在留カード等)の写しも添付してください。)